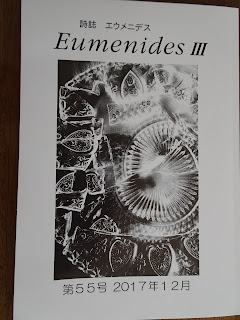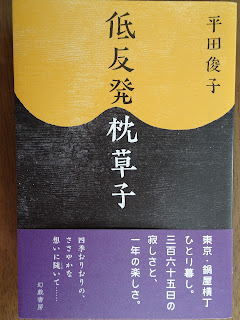杉中さんの特集と連続していて、なんだか気恥ずかしいのですが、特集にも論考を書いてくださった平居謙さん責任編集のオンラインジャーナル『新次元』8号が今日アップされ、そこに、インタビュー『大木潤子さんに聞く 最新詩集『石の花』までの足取りと今後の詩』が掲載されています。
http://geijutushinjigen.web.fc2.com/08ookisannnikiku.pdf
聞き手は平居謙さん。第一詩集『鳩子ひとりがたり』、第二詩集『有性無生殖』、昨年刊行した第三詩集『石の花』、そして今書いている連作の背景やコンセプトをお話ししています。平居謙さんの話術に引き出されて、忘れ去っていたことも思い出してお話しすることができました。
また、新作の拙作も、二篇、掲載されています。
お時間がありましたら、ご笑覧くださいましたら嬉しいです。
2018年1月30日火曜日
2018年1月29日月曜日
杉中昌樹さんのペーパーで「大木潤子特集」が出ました
杉中昌樹さんが、詩のペーパー「ポスト現代詩ノートvol.10」として、大木潤子特集を組んでくださいました。
最初、特集の企画を伺った時は、えぇ~?!と半信半疑でしたが、本当に出来上がりました。気恥ずかしいような、嬉しいような・・・。
企画編集をしてくださった杉中さん、そして、お忙しい中お時間を割いて、私の拙い詩について、素晴らしい詩と論考を寄せてくださった執筆者のみなさまに、感謝の気持ちで一杯です。
本当に有り難うございます。
豪華執筆陣の顔ぶれに、恐縮し、縮み上がるような思いでおります。
...
最初、特集の企画を伺った時は、えぇ~?!と半信半疑でしたが、本当に出来上がりました。気恥ずかしいような、嬉しいような・・・。
企画編集をしてくださった杉中さん、そして、お忙しい中お時間を割いて、私の拙い詩について、素晴らしい詩と論考を寄せてくださった執筆者のみなさまに、感謝の気持ちで一杯です。
本当に有り難うございます。
豪華執筆陣の顔ぶれに、恐縮し、縮み上がるような思いでおります。
...
ほんの一言ずつになってしまい、ちゃんと要約できるか自信がないのですが、掲載順に、内容を少しご紹介させて頂きます。
(執筆者のみなさま、要約が下手でしたら、失礼をどうぞ、お許しください。こんな短い要約でご紹介させて頂く失礼もどうぞお許しください・・・。)
***
☆最初に、新作の拙詩が6篇載っています。これまでとまた、ちょっと、作風の違う作品です。
☆朝吹亮二さん「石の夢」
うっとりするような御詩「石の夢」を寄せてくださいました。私の『石の花』の一部をエピグラフとして引用してくださっています。
☆鈴木ユリイカさん「プルプル震える詩と大木潤子さん」
『石の花』を読んでくださった時の心の動きがそのまま伝わってくる、美しいエッセイを書いてくださいました。
☆荻悦子さん「石の巣で孵った鳥―大木潤子『石の花』の印象」
詩集になる前の、書かれている途中の状態の『石の花』の中に潜って、そこから語るような、精緻な『石の花』論を書いてくださいました。
☆鈴村和成さん「魂が、戻ってきて見ている、大木潤子について」
第一詩集『鳩子ひとりがたり』に収められた最後の詩「鳩子の家」を、『石の花』や、連れあいの作品にも言及しながら、独自の切り口から論じてくださいました。
☆平居謙さん「『大木潤子の最現在』に関する走り書き」
第一詩集~第三詩集にも触れた後、まだ詩集に収められていない、今私が現在進行形で書いている作品群について紹介し、論じてくださいました。
☆阿部嘉昭さん「透明・映画・減喩―大木潤子について」
太宰治、ラブレー、バタイユなどへの言及の後、映画との関わり、そして『減喩』の視点から、第一詩集~第三詩集を、独自の分析で論じてくださいました。
☆福田拓也「大木潤子の詩集『石の花』の生成―証言と読解」
連れあいが、生活を共にしている人間として『石の花』の背景を、一方で一人の書き手として、『石の花』について、書いてくれました。
☆杉中昌樹さん「大木潤子とともに」
『石の花』を自在に引用しつつ、映画の一場面を観たような、不思議な読後感が残る散文詩を書いてくださいました。
***
企画編集の杉中さん、執筆してくださった皆様、本当に有り難うございました。
(執筆者のみなさま、要約が下手でしたら、失礼をどうぞ、お許しください。こんな短い要約でご紹介させて頂く失礼もどうぞお許しください・・・。)
***
☆最初に、新作の拙詩が6篇載っています。これまでとまた、ちょっと、作風の違う作品です。
☆朝吹亮二さん「石の夢」
うっとりするような御詩「石の夢」を寄せてくださいました。私の『石の花』の一部をエピグラフとして引用してくださっています。
☆鈴木ユリイカさん「プルプル震える詩と大木潤子さん」
『石の花』を読んでくださった時の心の動きがそのまま伝わってくる、美しいエッセイを書いてくださいました。
☆荻悦子さん「石の巣で孵った鳥―大木潤子『石の花』の印象」
詩集になる前の、書かれている途中の状態の『石の花』の中に潜って、そこから語るような、精緻な『石の花』論を書いてくださいました。
☆鈴村和成さん「魂が、戻ってきて見ている、大木潤子について」
第一詩集『鳩子ひとりがたり』に収められた最後の詩「鳩子の家」を、『石の花』や、連れあいの作品にも言及しながら、独自の切り口から論じてくださいました。
☆平居謙さん「『大木潤子の最現在』に関する走り書き」
第一詩集~第三詩集にも触れた後、まだ詩集に収められていない、今私が現在進行形で書いている作品群について紹介し、論じてくださいました。
☆阿部嘉昭さん「透明・映画・減喩―大木潤子について」
太宰治、ラブレー、バタイユなどへの言及の後、映画との関わり、そして『減喩』の視点から、第一詩集~第三詩集を、独自の分析で論じてくださいました。
☆福田拓也「大木潤子の詩集『石の花』の生成―証言と読解」
連れあいが、生活を共にしている人間として『石の花』の背景を、一方で一人の書き手として、『石の花』について、書いてくれました。
☆杉中昌樹さん「大木潤子とともに」
『石の花』を自在に引用しつつ、映画の一場面を観たような、不思議な読後感が残る散文詩を書いてくださいました。
***
企画編集の杉中さん、執筆してくださった皆様、本当に有り難うございました。
2018年1月28日日曜日
詩誌『Down Beat』の朗読会『Down Beat フォーラムⅧ』(@東京八重洲)に行ってきました
今日は、詩誌『Down Beat』の朗読会『Down Beat フォーラムⅧ』(@東京八重洲)に行ってきました!
同人の徳弘康代さんの新詩集『音をあたためる』出版を記念しての朗読会。テーマは「生と死のあわいをえがく」。
徳弘さんのご朗読を中心とした第一部、同人全員による、「生と死のあわいをえがく」のテーマに沿った作品朗読とディスカッションの第二部、どちらも充実していて、とても豊かな午後を過ごさせて頂きました。
第一部の徳弘さんのご朗読は、「あっこんな風に読むんだ!」と、はっとする瞬間が何度もあってスリリングでした。やっぱり、朗読を聴くって、貴重な経験だなあと思いました。
第二部、全員の作品と朗読がとても良かったし、親を亡くす経験を中心としたディスカッションがとても興味深かったです。はっとさせられることが多かった。...
あ~朗読会っていいなあ、パネルディスカッションも面白いなあ、また行きたいなあ! と、帰り道、次回が今から楽しみになってしまいました。
資料も印刷がとても綺麗で、珍しい、明治時代の教科書のフォントが使われていたり、行き届いていて、すごく良かった! 写真は資料の表紙です。
あ~楽しかった~!
同人の徳弘康代さんの新詩集『音をあたためる』出版を記念しての朗読会。テーマは「生と死のあわいをえがく」。
徳弘さんのご朗読を中心とした第一部、同人全員による、「生と死のあわいをえがく」のテーマに沿った作品朗読とディスカッションの第二部、どちらも充実していて、とても豊かな午後を過ごさせて頂きました。
第一部の徳弘さんのご朗読は、「あっこんな風に読むんだ!」と、はっとする瞬間が何度もあってスリリングでした。やっぱり、朗読を聴くって、貴重な経験だなあと思いました。
第二部、全員の作品と朗読がとても良かったし、親を亡くす経験を中心としたディスカッションがとても興味深かったです。はっとさせられることが多かった。...
あ~朗読会っていいなあ、パネルディスカッションも面白いなあ、また行きたいなあ! と、帰り道、次回が今から楽しみになってしまいました。
資料も印刷がとても綺麗で、珍しい、明治時代の教科書のフォントが使われていたり、行き届いていて、すごく良かった! 写真は資料の表紙です。
あ~楽しかった~!
2018年1月24日水曜日
山下澄人さんの『ほしのこ』と『を待ちながら』
小説は門外漢ですが、最近の日本は小説がすごく面白くなっているので、小説についても時々書いてみようかな、と思います。
昨年末読んだ、山下澄人さんの、芥川賞受賞第一作「ほしのこ」(文藝春秋刊)は、 言葉で書かれているのにまるで映像のように、鮮やかに場面が目に浮かび、美しい映像詩を観たような感動が後に残りました。人物間の境界が曖昧になる世界は山下さんならではの非常に斬新な書き方で、戦うことの無意味さがひしひしと伝わってきました。
山下澄人さんの新作では、「新潮」10月号掲載の戯曲『を待ちながら』もとても良かったです。
昨年末読んだ、山下澄人さんの、芥川賞受賞第一作「ほしのこ」(文藝春秋刊)は、 言葉で書かれているのにまるで映像のように、鮮やかに場面が目に浮かび、美しい映像詩を観たような感動が後に残りました。人物間の境界が曖昧になる世界は山下さんならではの非常に斬新な書き方で、戦うことの無意味さがひしひしと伝わってきました。
山下澄人さんの新作では、「新潮」10月号掲載の戯曲『を待ちながら』もとても良かったです。
ベケットの『ゴドーを待ちながら』では、「待つ」という動詞に対して目的語(ゴドー)が明記されていますが、「を待ちながら」では目的語が無になっていて、何かを待っていると、登場人物たちに意識すらされていないことが、非常に興味深かったです。
ベケットの『ゴドー』には何か、希望のようなものを、ほのかに待つような感触がありますが、『を待ちながら』では待っているものはもっと怖いものであることを、『アンネの日記』(非日常の中の日常とも言える箇所が選ばれていて印象的。今私たちが日常と思っているものはすでに非日常なのではないかと…。)の朗読と、154ページ下段の「こども」の台詞が示唆しているように感じました。タイトルの『を待ちながら』の、「待つ」という動詞の主語は何か恐ろしい事態であり、目的語は、それを知らずに生きている私たち自身なのではないか、と感じ、戦慄しました。音楽家の、最後の台詞もまるで散文詩のようで、深く印象に残りました。2018年1月22日月曜日
昨日は梅の木を剪定
昨日は梅の枝を少し剪定しました。
垣根の病気でいろいろ調べているうちに、これまで、植木屋さん達が変な時期に変な切り方をしたり、切らなければならないところを切らずにいたりした、という怖い事実が次第に判明。垣根は病気になり、他にも大事にしていた木が一本枯れてしまった・・・。
そこで、自分でやってみようということで、植木剪定の本を買い込んでいます。
「花芽が確定したら、徒長枝は5~6芽を残して、外芽のすぐ上で切る」
云々、といった表現がようやくわかるようになってきました。...
昨日は細い枝を切るだけだったからいいけど、のこぎりを使うような作業が出来るようになるのか・・・。
不安はあるけれど当面、頑張ってみます。
写真は昨日早速間違って切り落とした(苦笑)、花の芽があった枝。
捨てるのは可愛そうなのでマグカップに挿しました。
芽はまだすご~く小さい。
咲くかなあ~無理かなあ~
マグカップはもうかれこれ17年以上前にスペインに行った時、陶器屋の前でバケツにごろごろ入って投げ売りみたいにして売っていたもの。
すごく気に入っていたのだけど、アルカリ性の洗剤を溶くのに使ったら、化学反応したのか、縁がぼろぼろ欠けてしまった・・・。
が、思い入れがあるのでそのまま使っています。
垣根の病気でいろいろ調べているうちに、これまで、植木屋さん達が変な時期に変な切り方をしたり、切らなければならないところを切らずにいたりした、という怖い事実が次第に判明。垣根は病気になり、他にも大事にしていた木が一本枯れてしまった・・・。
そこで、自分でやってみようということで、植木剪定の本を買い込んでいます。
「花芽が確定したら、徒長枝は5~6芽を残して、外芽のすぐ上で切る」
云々、といった表現がようやくわかるようになってきました。...
昨日は細い枝を切るだけだったからいいけど、のこぎりを使うような作業が出来るようになるのか・・・。
不安はあるけれど当面、頑張ってみます。
写真は昨日早速間違って切り落とした(苦笑)、花の芽があった枝。
捨てるのは可愛そうなのでマグカップに挿しました。
芽はまだすご~く小さい。
咲くかなあ~無理かなあ~
マグカップはもうかれこれ17年以上前にスペインに行った時、陶器屋の前でバケツにごろごろ入って投げ売りみたいにして売っていたもの。
すごく気に入っていたのだけど、アルカリ性の洗剤を溶くのに使ったら、化学反応したのか、縁がぼろぼろ欠けてしまった・・・。
が、思い入れがあるのでそのまま使っています。
2018年1月20日土曜日
詩誌「エウメニデスⅢ」55号(2017年12月刊)、先鋭な一冊
ちょっとばたばたしていて、UPが遅くなりましたが、お正月早々に、詩誌「エウメニデス」55号(編集発行・小島きみ子さん)が届きました。超豪華執筆陣! 先鋭な力作揃い! 贅沢な一冊。書評欄の充実も印象的。現代詩の最前線を走る詩誌。55号という息の長さも凄い!
2018年1月1日月曜日
さねさし相模の会の忘年会
話は前後するんだけど、12月30日は「さねさし相模の会」という忘年会で楽しく過ごした。詩人、歌人が30人集まり、二次会はカラオケ。以前から感じているのだけど、詩人はみんな歌がうまい。詩と歌はやっぱり通じているのかな。
明けましておめでとうございます!
明けましておめでとうございます! 本年もどうぞよろしくお願い致します。 写真は、初詣に行った近所の神社の提灯飾りと、冬の夕日を浴びる近所の山です。山の麓は住宅地なので、家や電線が入らないように写すのが大変でした。笑
2017年12月23日土曜日
陶原葵さんの『帰、去来』(思潮社、4月29日刊)
陶原葵さんの『帰、去来』(思潮社、4月29日刊)は、「私は今こういう言葉が読みたかった、こういう詩が読みたかった」と心の中で唱えながら読んだ。
ある程度長い年月を生きて、数々の辛い経験が、生のままではなく、濾過されて、純度の高い言葉に結晶している、そういう美しさが心に沁みる。
身なし貝 を 拾いに
(「窟」)
...
ある程度長い年月を生きて、数々の辛い経験が、生のままではなく、濾過されて、純度の高い言葉に結晶している、そういう美しさが心に沁みる。
身なし貝 を 拾いに
(「窟」)
...
貝殻、ではなく、身なし貝、と言うことで、そこにないものが意識される。ないものを拾いにいくような徒労感。
毎日 手おくれ気味に
なにか 待っていたのだが
おそらく
大きな約束をわすれている
という四行が含まれている作品「柱」を終える次の三行は何度読んでも心をえぐる。
煤けた虚に
翅のない蝶
眼をあけて
たった三行、十五文字の持つ力。
この詩行は、「著莪」の、
鏡の裏に 階段をおりてくる痛みが映る
展翅板に刺されたまま 発光する蛍よ
とも呼応している。この詩行も、凄絶な美しさだ。
沈潜した徒労感、とも呼びたくなる独得の感覚は、次の詩行にも色濃く感じられる。
石畳 すきまの土から
錆びたものがいっせいに発芽している
(「帰、去来」)
かくしていた霧灰に洗われた
家のおくには
消えた線香が立って
(「渕」)
詩集の最後に収められた「20×5」からはしかし、絶望の中から、透明な光のようなものも射してくるのだった。
透蚕の浄心 手の中につつみ
なかそらにむけて
ゆびをいっぽんずつ
ひらいていく
いつか記憶がほとびる
そこからの綻びを待つ日
毎日 手おくれ気味に
なにか 待っていたのだが
おそらく
大きな約束をわすれている
という四行が含まれている作品「柱」を終える次の三行は何度読んでも心をえぐる。
煤けた虚に
翅のない蝶
眼をあけて
たった三行、十五文字の持つ力。
この詩行は、「著莪」の、
鏡の裏に 階段をおりてくる痛みが映る
展翅板に刺されたまま 発光する蛍よ
とも呼応している。この詩行も、凄絶な美しさだ。
沈潜した徒労感、とも呼びたくなる独得の感覚は、次の詩行にも色濃く感じられる。
石畳 すきまの土から
錆びたものがいっせいに発芽している
(「帰、去来」)
かくしていた霧灰に洗われた
家のおくには
消えた線香が立って
(「渕」)
詩集の最後に収められた「20×5」からはしかし、絶望の中から、透明な光のようなものも射してくるのだった。
透蚕の浄心 手の中につつみ
なかそらにむけて
ゆびをいっぽんずつ
ひらいていく
いつか記憶がほとびる
そこからの綻びを待つ日
2017年12月19日火曜日
野菜くずのお出汁
ここ何ヶ月かハマってるのがこれ、「野菜くずのお出汁
野菜くずを瓶に入れて、水につけて一日~二日置くだけ
普段の出汁にこれをプラスするとすごく奥行きのある味
東京新聞の生活欄で紹介されていて、最初読んだ時は「
以来毎日、野菜くずは捨てずに水に浸す習慣に。
特に美味しく出るのが玉ねぎの皮、キャベツの芯、人参
良かったら、試してみてください♪
野菜くずを瓶に入れて、水につけて一日~二日置くだけ
普段の出汁にこれをプラスするとすごく奥行きのある味
東京新聞の生活欄で紹介されていて、最初読んだ時は「
以来毎日、野菜くずは捨てずに水に浸す習慣に。
特に美味しく出るのが玉ねぎの皮、キャベツの芯、人参
良かったら、試してみてください♪
2017年12月18日月曜日
法橋太郎さん『永遠の塔』(思潮社)
2月25日発行、法橋太郎さん『永遠の塔』(思潮社)。
帯に、『山上の舟』から18年とあって、感慨深かった。もうそんなに経ってしまったのか。『山上の舟』を読んだ時のずっしりした印象は今も変わらず私の中にあって、法橋さんが第二詩集を出されたことは、とても嬉しい出来事だった。
『山上の舟』からの18年は、詩人にとって苦難に満ちた日々だったのではないだろうか。『永遠の塔』には、苦渋を舐め、深淵に迷った者からのみ発せられるような、深い叫びが聞こえてくる。神に見捨てられたと絶望しながらも、なおも神へと呼び掛ける声を私は聞く。その声は、何処ともしれぬ、不思議な場所から届く。
...
帯に、『山上の舟』から18年とあって、感慨深かった。もうそんなに経ってしまったのか。『山上の舟』を読んだ時のずっしりした印象は今も変わらず私の中にあって、法橋さんが第二詩集を出されたことは、とても嬉しい出来事だった。
『山上の舟』からの18年は、詩人にとって苦難に満ちた日々だったのではないだろうか。『永遠の塔』には、苦渋を舐め、深淵に迷った者からのみ発せられるような、深い叫びが聞こえてくる。神に見捨てられたと絶望しながらも、なおも神へと呼び掛ける声を私は聞く。その声は、何処ともしれぬ、不思議な場所から届く。
...
おれの見えないところで風が吹いた。その風
がおれの身体を吹き抜けてゆくとき、古い時
代の印刷機が湖に沈んでいった。
(「風の記録」)
風が吹き抜ける今と、湖に沈む印刷機が生きた「古い時代」とが、詩行の中で出逢う。時間を自在に往き来する感覚がここにある。
永遠に過ぎ去るのは今だけか。身体の内と外
は空気より透明な廃墟だ。宇宙が音を鳴らし
た。水垣には藻が色づき、壊れた水車が、軋
み廻った。少年のむしりとった草が水垣を流
れ去った。
(『永遠の塔』)
宇宙の鳴らす音と、壊れた水車の軋む音ともまた、詩行の中で交響する。遠い音と近い音との共存は、空間をも自在に往き来する詩人の意識によってもたらされているのではないだろうか。
荒川沿いの小径を歩きつづけた。足首を痛め
たまま、二月のドラムカンに燃える火を見た。
この世の最後かと思うような夕暮れのあと、
夜が明けるまでの小径にいくつもの水たまり
がいくつもの貌となって現れては消えた。朝
には黒い雨が降った。
(『自然の摂理』)
荒川沿いという、現実の地名、「足首を痛めた」という、個人的な感覚から一気に、いつ、どことも知れぬ場所へと読者は連れ去られる。
深淵へ深淵へと沈んだ力をばねにして、とてつもない広大な時空を一瞬にして移動する感覚がこの詩集にはある。そのスケールの大きさに圧倒される。
今もFacebookで旺盛に作品を発表し続けている法橋さんの、次の詩集が今から楽しみだ。
がおれの身体を吹き抜けてゆくとき、古い時
代の印刷機が湖に沈んでいった。
(「風の記録」)
風が吹き抜ける今と、湖に沈む印刷機が生きた「古い時代」とが、詩行の中で出逢う。時間を自在に往き来する感覚がここにある。
永遠に過ぎ去るのは今だけか。身体の内と外
は空気より透明な廃墟だ。宇宙が音を鳴らし
た。水垣には藻が色づき、壊れた水車が、軋
み廻った。少年のむしりとった草が水垣を流
れ去った。
(『永遠の塔』)
宇宙の鳴らす音と、壊れた水車の軋む音ともまた、詩行の中で交響する。遠い音と近い音との共存は、空間をも自在に往き来する詩人の意識によってもたらされているのではないだろうか。
荒川沿いの小径を歩きつづけた。足首を痛め
たまま、二月のドラムカンに燃える火を見た。
この世の最後かと思うような夕暮れのあと、
夜が明けるまでの小径にいくつもの水たまり
がいくつもの貌となって現れては消えた。朝
には黒い雨が降った。
(『自然の摂理』)
荒川沿いという、現実の地名、「足首を痛めた」という、個人的な感覚から一気に、いつ、どことも知れぬ場所へと読者は連れ去られる。
深淵へ深淵へと沈んだ力をばねにして、とてつもない広大な時空を一瞬にして移動する感覚がこの詩集にはある。そのスケールの大きさに圧倒される。
今もFacebookで旺盛に作品を発表し続けている法橋さんの、次の詩集が今から楽しみだ。
2017年12月15日金曜日
松尾真由美さんの『花章ーディベルティメント』(思潮社)
2月20日発行、松尾真由美さんの「花章-ディベルティメント」(思潮社)。
とても好きな詩集で、携えて歩くことが多かったので、帯が少し擦れてしまった。特に好きなところにつけた付箋も、外すと後で困ってしまうから、そのままで写真を撮りました。新しい時に、写真を撮っておけば良かった。
松尾さんの詩には私はいつも濃厚な官能性を感じるのだけれど、一方で諧謔もあったり、一筋縄ではいかない。今回の詩集は、官能性と同時に「死」を、そして、生から物(無機物)へと向かう動きとを感じた。
後は散っていくだけの...
花弁なのだから
蛇のめまいのよう
ここにいて
石になる
(「描ききれない溺者の譜」)
とても好きな詩集で、携えて歩くことが多かったので、帯が少し擦れてしまった。特に好きなところにつけた付箋も、外すと後で困ってしまうから、そのままで写真を撮りました。新しい時に、写真を撮っておけば良かった。
松尾さんの詩には私はいつも濃厚な官能性を感じるのだけれど、一方で諧謔もあったり、一筋縄ではいかない。今回の詩集は、官能性と同時に「死」を、そして、生から物(無機物)へと向かう動きとを感じた。
後は散っていくだけの...
花弁なのだから
蛇のめまいのよう
ここにいて
石になる
(「描ききれない溺者の譜」)
花弁の中に死が潜んでいて、しかし死ぬだけではなく、「石になる」、この不思議な行程。
耳を澄ませば
聞こえない内部の灰
(「不分明な声の熱度」)
灰が死の隠喩もしくは換喩としてでだけでなく、灰という、生命を持たない物体としても立ち現れてくる。
風が吹いて
水はながれて
漂流する小舟の形で
来歴を消していく
(「わずかに剥がれる逸話のように」)
来歴を消す、生命を持つ者としての、それまで持った時間を消す。その時やはり存在は無機物的になるのではないだろうか。
無為の糧
零となる日を
差しだすことの
それは晴れやかな
異端の白い芯である
(「葉群れのかすかな晶度へと」)
無為、零。時間を遡行して、いなかったところに戻っていくような感覚がここにある。
言葉もまた、松尾さんの詩の中では、貨幣のように、意味を乗せて流通する存在であることをやめて、音として、作品内で響き合う楽器として、闇の中でじっと目を見開く存在になるようだ。「ディヴェルティメント」という副題が示唆するように、室内楽を思わせるその響きは、音楽作品の構造のような造形性から、紙という平面から立ち上がる造形芸術のようにも感じられる。
言葉が、記号としての生を一度死んで、触れることのできる、質感と奥行きを持ったマッス(塊)であるかのように存在し始める。そこに松尾さんの詩の官能性がある。官能とは何よりも、触れるところから始まる感覚だからだ。
耳を澄ませば
聞こえない内部の灰
(「不分明な声の熱度」)
灰が死の隠喩もしくは換喩としてでだけでなく、灰という、生命を持たない物体としても立ち現れてくる。
風が吹いて
水はながれて
漂流する小舟の形で
来歴を消していく
(「わずかに剥がれる逸話のように」)
来歴を消す、生命を持つ者としての、それまで持った時間を消す。その時やはり存在は無機物的になるのではないだろうか。
無為の糧
零となる日を
差しだすことの
それは晴れやかな
異端の白い芯である
(「葉群れのかすかな晶度へと」)
無為、零。時間を遡行して、いなかったところに戻っていくような感覚がここにある。
言葉もまた、松尾さんの詩の中では、貨幣のように、意味を乗せて流通する存在であることをやめて、音として、作品内で響き合う楽器として、闇の中でじっと目を見開く存在になるようだ。「ディヴェルティメント」という副題が示唆するように、室内楽を思わせるその響きは、音楽作品の構造のような造形性から、紙という平面から立ち上がる造形芸術のようにも感じられる。
言葉が、記号としての生を一度死んで、触れることのできる、質感と奥行きを持ったマッス(塊)であるかのように存在し始める。そこに松尾さんの詩の官能性がある。官能とは何よりも、触れるところから始まる感覚だからだ。
2017年12月13日水曜日
平田俊子さんの「低反発枕草子」(幻戯書房)
読んで印象に残った本を、FBで随時アップしていく予定でいたのだけど、今年は、冬は次から次へと心配事、春からは垣根の病気に追われ、アップできないままになってしまった。今もまだ垣根に時間がとられていて、一言ずつになってしまうけれど、本を通して今年の読書を振り返ってみたい。
1月15日発行、平田俊子さんのエッセイ集「低反発枕草子」を読んだ時は次から次へと心配事が起きている真っ最中。その中で、この本にとても癒やされた。
特に面白かったのが、日常の、本当に些細な出来事を書いた作品。レトルトカレーの注意書きの読み比べや、「アイツ」(ごきぶり)との格闘など、通常は文字にされないまま忘れ去られてしまうような小さな出来事が鮮やかに描かれている。中でも、底が濡れて染みが付いた宅配の段ボール、山手線のホームに落ちていた薄汚れたボールペンから始まる二篇には心を揺さぶられた。
1月15日発行、平田俊子さんのエッセイ集「低反発枕草子」を読んだ時は次から次へと心配事が起きている真っ最中。その中で、この本にとても癒やされた。
特に面白かったのが、日常の、本当に些細な出来事を書いた作品。レトルトカレーの注意書きの読み比べや、「アイツ」(ごきぶり)との格闘など、通常は文字にされないまま忘れ去られてしまうような小さな出来事が鮮やかに描かれている。中でも、底が濡れて染みが付いた宅配の段ボール、山手線のホームに落ちていた薄汚れたボールペンから始まる二篇には心を揺さぶられた。
登録:
投稿 (Atom)